子どもから大人までバイオリンを学んでいくのに必ず必要なバイオリン教本!
でも、レベル別にたくさんのバイオリン教本があって、どれを選んだら良いのか迷ってしまいますよね。
そこで今回は、バイオリン教本をレベルや目的別にご紹介!
進度の目安や初心者から上級者向けのおすすめなバイオリン教本、さらにバイオリン教本の特徴など、詳しく解説していきます。
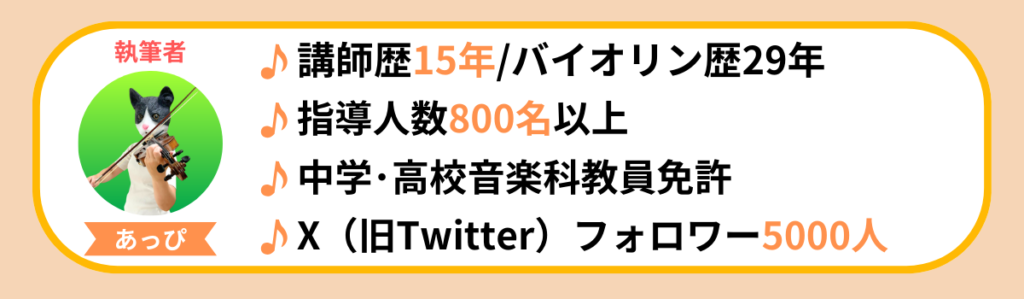
バイオリン教本とは
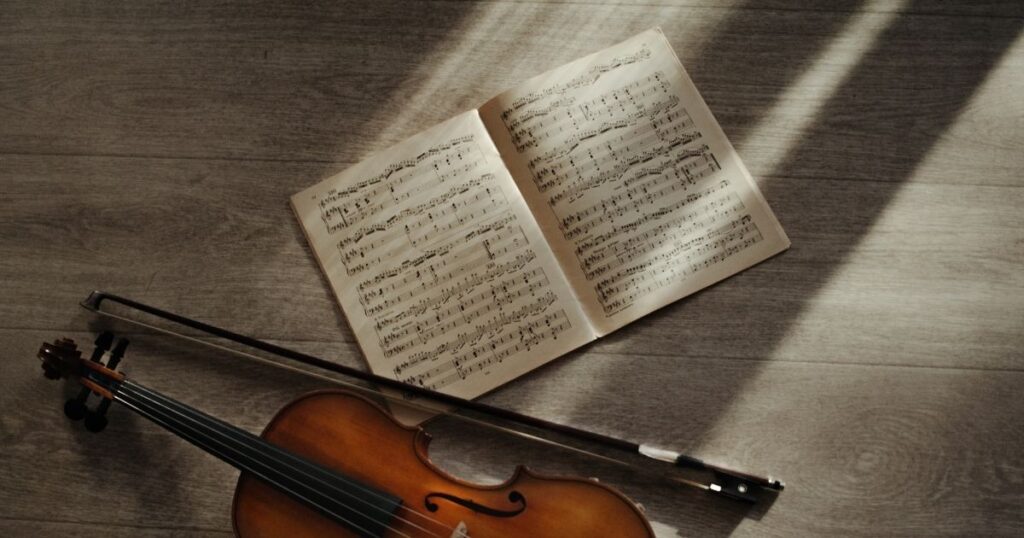
そもそもバイオリン教本とは、バイオリンの演奏テクニックを段階的に身につけるための教材で、学校の教科書やドリルのような存在です。
バイオリン教本は上達に欠かせませんので、ほとんどの先生がレッスンで使用しています。
バイオリン教本と言えば、有名なのは3つの教材です。
- スズキメソードバイオリン教本
- 新しいヴァイオリン教本
- 篠崎ヴァイオリン教本
一般的にはこの3つのうちのどれかをメイン教材として使用します。
こちらは教科書的な役割です。
その一方で、ドリルのような役割を持つ教本は、エチュードと呼ばれます。
エチュードは、日本語では「練習曲」と呼ばれます。
それぞれの練習曲でスタッカートや移弦など、学ぶべきテーマがあり、苦手な奏法を克服するなど、自分に必要なものを選んで進めることもできます。
バイオリン初心者・中級者・上級者のレベルの目安

バイオリン教本は、自分のバイオリンの演奏技術や目的によって使うべきものが変わっていきます。
(先生に問答無用で指定されてしまうケースもあります…)
とはいえ、自分が今どのレベルにいるのか、わかりにくいですよね。
ここでは、バイオリンのレベルの目安を3つに分けて解説していきます。
バイオリン初心者のレベルの目安
バイオリン初心者の場合、まずは正しいバイオリンの構え方や弓の持ち方・動かし方を身につけることが最優先です。
その上で、1stポジションで様々な音階や曲目を弾けるようにしていきたいですね!
また、重音(2つの音を同時に鳴らすこと)や音の強弱をつけることも課題になってきます。
バイオリン中級者のレベルの目安
ポジション移動(左手の位置の移動)やビブラート、フラジオレット(指で弦を触って倍音を響かせる奏法)などの複雑な奏法が身に付いている方は中級者と言って良いでしょう。
中級者の方が弾ける曲の目安は、以下の通りです。
- タイスの瞑想曲/マスネ
- 2つのヴァイオリンのための協奏曲/バッハ
- チャルダッシュ/モンティ
これらの曲で音程を安定させ、完成に持っていける方であれば、ソロだけでなく、アンサンブルやオーケストラにも挑戦できるようになります。
バイオリン上級者のレベルの目安
さらに高いポジション移動(8ポジション以上)や3度や6度、オクターブの重音などをこなしていけるレベルの方は、上級者と言って良いでしょう。
上級者の方が弾ける曲の目安は、以下の通りです。
- シャコンヌ/ヴィタリ
- メンデルスゾーン/バイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64
- ツィゴイネルワイゼン/サラサーテ
このレベルになると、オーケストラで1stバイオリンをバリバリ弾けるようになります。
バイオリン初心者におすすめの教本

まずは、初心者の方のおすすめのバイオリン教本をご紹介します!
結論から言うと、筆者あっぴのおすすめは新しいバイオリン教本です。
バイオリンの3大教本と呼ばれる、指導者の間でも評価が高いものが以下の通りです。
- スズキバイオリン教本
- 篠崎バイオリン教本
- 新しいバイオリン教本
それぞれの特徴を詳しく解説していきます。
鈴木ヴァイオリン指導曲1~3巻
スズキメソードから生まれた全10巻の教本です。
難易度が緩やかに上がっていき、有名な曲がたくさん載っているのが特徴です。
また、CDが付いているので、模範演奏を聴くことができます。
ただし、音階などの基礎的な練習はほとんど載っておらず、曲をどんどん進めていくスタイル。
基礎練習が苦手な方、有名な曲を演奏して、楽しみながら進めたいという方におすすめです。
篠崎ヴァイオリン教本1・2巻
図と共に説明がしっかり載っている全4巻のバイオリン教本です。
1冊のボリュームが多いのですが、1巻が終わる頃には、様々な左手のおさえ方を習得できるようになっています。
独学でバイオリンを学んでいる方や、基礎からゆっくり丁寧に進めたい方におすすめです。
2巻からは曲が増え、二重奏になっているので、先生と一緒にアンサンブルをしながら学ぶことができます。
後半は、カイザーのエチュードも載っています。
そのため、補助教材を使わずに1冊で進めていく先生が多いです。
新しいバイオリン教本1・2巻
筆者あっぴが最もおすすめするのが、新しいヴァイオリン教本です。
基礎的な練習と短い曲が、交互に登場し、とてもよく考えられた全6巻のバイオリン教本です。
各ナンバーでそれぞれ課題が設定されていて、順番に進めていけば演奏に必要なテクニックを取りこぼしなく身につけることができます。
また、他の教本と比べてスピード感もあるので、上手に使えば早く上達することができるのも、筆者あっぴがおすすめする理由です。
お子さんはもちろん、大人から始めた方にも、個人的にはこちらで基礎からしっかり学んでいただくのがベストだと考えています!
カイザー「36の練習曲」
ある程度、色んな音階に慣れてきた頃に並行していくエチュードです。
上で紹介した教本のそれぞれ2巻の途中くらいから始めるのが良いです。
それぞれの練習曲で課題が設定されていて、その技術を1曲で徹底的に学ぶことができます。
ただし1曲が長いので、どうしても練習に時間はかかります。
どのナンバーをどの程度取り組むかについては先生のアドバイスが必要です。
バイオリン中級者におすすめの教本

続いて、中級者向けのバイオリン教本をご紹介します。
先ほどと同じように、それぞれ詳しく解説していきます!
鈴木ヴァイオリン指導曲4~7巻
ひとつひとつの曲のボリュームが多くなり、1曲あたり2~3ページのものが増えます。
デメリットとして、序盤と終盤の曲のレベルがあまり変わらないという点がよく指摘されていますので、全ての曲をやらないという選択肢もあります。
基礎的な練習は少ないので、応用力をつけて上達したい方はこの教本だけでは足りません。
音階教本やエチュードと並行して進める必要があります。
篠崎ヴァイオリン教本3巻
音階やエチュード、曲がこの1冊で完結するバイオリン教本です。
他の教本を買い足さなくても十分です。
中身の半分ほどがポジション移動の練習なので、ポジション移動を習得しやすいです。
新しいバイオリン教本3・4巻
3巻では、ポジション移動やビブラート・フラジオレットの練習が出てきます。
基礎的な練習内容がとても充実しているので、筆者あっぴはレッスンで上級者の復習としてもよく取り扱っています。
基礎的な練習と曲のバランスが良いので、クラシックがお好きな方は全て取り組むのも良いでしょう。
4巻では、3巻よりも高いポジションでの演奏に慣れることに重点を置いています。
4巻からは進度がゆっくりになるので、曲を弾きながら高いポジションに慣れることができます。
個人的には、ポジションチェンジがしっかりできるようになったら、教本以外のお好きな曲にもどんどんチャレンジしてほしいです^^
ヴァイオリン音階教本/小野アンナ
バイオリンを正確な音程で弾くために必要なのが、音階練習です。
左手の指の配置をしっかり理解しながら音階を弾けるようにしておくと、曲の練習に入った時に応用が効くようになります。
ポジション移動の練習も、この教本でしっかりおさえておきましょう。
筆者あっぴは10~14ページは必ずレッスンで扱います!
他にもやるべきページはたくさんあって、バイオリンを演奏する人なら必ず持っていて欲しい一冊です。
クロイツェル 42の練習曲
バイオリンを演奏するために必要な基本の奏法に加え、難易度の高い重音練習も載っており、ボリュームのあるエチュードです。
全曲弾ければ、どんな曲でもとりあえず一通り弾けるようになると言われているので、バイオリンが上手になりたいという方は取り組んでください!
オーケストラへの入団を考えている方は特に必須です。
ただし、こちらも練習に時間を要しますので、先生と相談しながらすすめるのが良いでしょう。
独学での練習は絶対におすすめしません。
バイオリン上級者におすすめの教本

最後は上級者向けのバイオリン教本をご紹介します!
それぞれの特徴などを詳しく解説していきます。
鈴木ヴァイオリン指導曲8~10巻
さらに1曲のボリュームが増え、9・10巻ではモーツァルトのバイオリン協奏曲が登場します。
それぞれの曲を弾くための簡単な練習はありますが、それだけでは足りません。
そのため、他の音階教本やエチュードと併せて進める必要があります。
また、筆者あっぴとしてはモーツァルトのコンチェルトに取り組むのであれば別の出版社からでている楽譜をおすすめします。
同じ意見の先生は多いと思いますので、購入の際は先生に相談してみてください。
篠崎ヴァイオリン教本4
さらに高いポジション移動の練習が加わります。
とはいえ、鈴木ヴァイオリンや新しいバイオリン教本より易しいです。
ひとつひとつじっくりゆっくり進めたい方にはおすすめです。
もう少し難しいことに挑戦したい方は、他のバイオリン教本をおすすめします。
新しいバイオリン教本5・6
5巻では、3度6度オクターブの練習や、さらに高いポジション移動の練習が出てきます。
6巻になると、10度の重音練習が出てくるので、難易度が高くなります。
6巻まで進むと、難易度が高い曲にも挑戦しやすくなるので、これから難しい曲に挑戦したい方におすすめです。
カールフレッシュ
音階練習の全てが詰まった音階教本で、世界中の音大生やプロも愛用しています。
上級者向けの内容になりますので、ご自身の判断で実践することはおすすめしません。
余談ですが、本自体が分厚く重いので、持ち運びには適していません(;’∀’)
ローデ 24のカプリース
クロイツェルよりも少し難易度が上がったエチュードです。
曲のような美しいメロディーがあり、発表会等で弾かれることもしばしばあります。
取り組む場合はクロイツェル教本を8割以上終えていることが好ましいです。
ドント 24の練習曲とカプリース
ローデよりもさらに高い演奏技術を身につけるためのエチュードです。
音大生やプロにも懸念されるレベルの内容となっています(;’∀’)
軽い気持ちで挑戦してみたい方は腱鞘炎にならないようご注意ください。
バイオリン教本のレベル別解説まとめ
ここまで、バイオリン教本についてまとめました。
- バイオリン教本とは、学校で言う教科書やドリルのようなもの
- バイオリン学習者のレベル別の目安
- レベル別おすすめバイオリン教本
自分にぴったりなバイオリン教本を見つかりましたか?
しつこいようですが、筆者あっぴのおすすめは新しいヴァイオリン教本です!
私自身はスズキの教本を全てやりましたが、なかなか上達せず、それだけで上達するのはかなり難しいなと感じています。
教本を使ってどのように上達していったら良いのか、まだヒントが足りないと感じている方は、メルマガにて無料動画レッスンを配信しています。
参考にしていただけたら嬉しいです^^
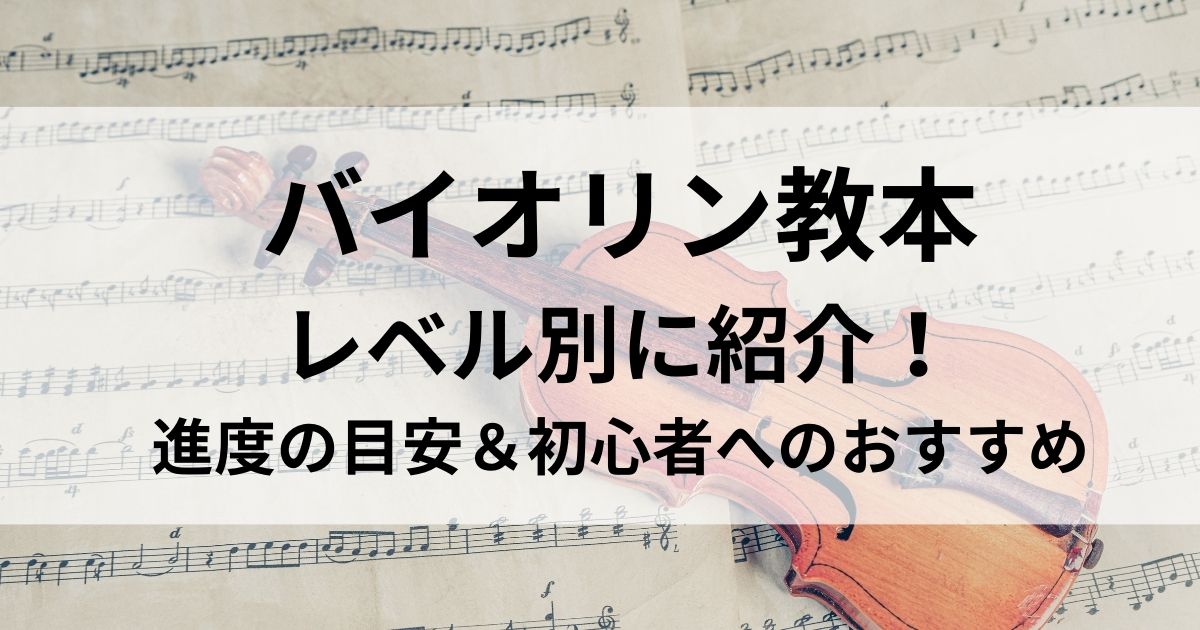



























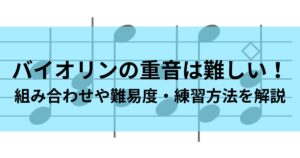
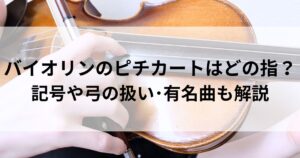
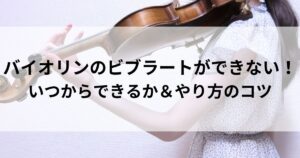
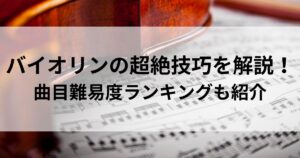
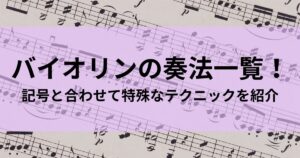
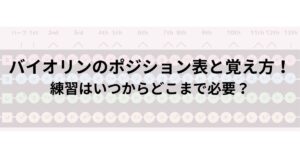

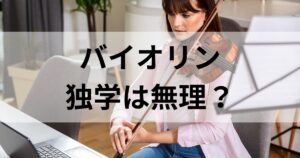
コメント